導入
「変化の割合」と聞くと、“傾き”のことだと思う人が多いですよね。
一次関数のときは確かにそれで正解でした。
でも、y=ax²のような関数では傾きが1つに決まらないんです。
なぜなら、グラフがまっすぐではなく「カーブしている」からです。
今までの一次関数では、どこを見ても同じ上がり方・下がり方でした。
しかし二次関数では、区間によって上がり方のスピードが違うため、
「変化の割合」も区間ごとに変わることになります。
ポイント①:まず「変化の割合=(yの増加量)÷(xの増加量)」を書く
どんな関数でも、「変化の割合」とはこの式から始まります。変化の割合=yの増加量/xの増加量
この式を書くだけで、やるべきことが明確になります。
- xがどのくらい増えたか(xの増加量)
- yがどのくらい増えたか(yの増加量)
を順番に求めればOKです。
ポイント②:一次関数との違いを整理する
| 関数の種類 | グラフの形 | 変化の割合の特徴 |
|---|---|---|
| 一次関数 | 直線 | どの区間でも同じ(一定) |
| y=ax² | 放物線 | 区間によって変わる(一定ではない) |
一次関数では「傾き=変化の割合」でしたが、
y=ax²では「区間ごとの平均的な上がり方・下がり方」を見るイメージです。
ポイント③:例題で確認してみよう
例題)y=x² において、xが1から3まで変化するときの変化の割合を求めなさい。
【解き方】
まず式を書く:変化の割合=yの増加量/xの増加量
xの増加量:3−1=2
yの増加量:3²−1²=9−1=8
したがって、変化の割合=8/2=4
✅ 答え:4
ポイント④:xの位置が変わると符号も変わる
たとえば、同じ関数 y=x² で
xが−3から−1まで変化するときの変化の割合を求めてみます。
xの増加量:−1−(−3)=2
yの増加量:1−9=−8変化の割合=−8/2=−4
✅ 答え:−4
右側(正のx)では正の値、左側(負のx)では負の値になりました。
放物線が左右対称なため、傾きの符号も反対になります。
まとめ
- 「変化の割合」は yの増加量xの増加量xの増加量yの増加量 で求める。
- 一次関数では常に一定、y=ax²では区間によって変わる。
- xが負のときは変化の割合が負、xが正のときは正になる。
- 放物線は左右対称なので、符号がちょうど反対になる。


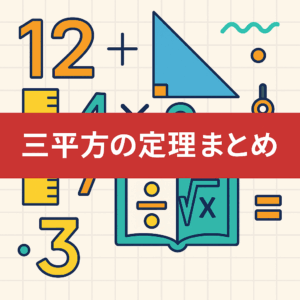
コメント