導入
y=ax²の変域って今までと求め方が違って難しく感じませんか?
今ままでと何が違うかを考えると理解しやすくなります。
一次関数(直線)のときは、
xが増えるにつれてずっと上がるかずっと下がるかのどちらかでした。
だから、xの最大・最小がそのままyの最大・最小になっていました。
でも、y=ax² のグラフは「放物線」。
曲がるので、xの範囲(変域)によって
yの増え方・減り方が変わってきます。
ポイント①:直線と放物線の違い
| 関数の種類 | グラフの形 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一次関数 | 直線 | 上がりっぱなし or 下がりっぱなし |
| y=ax² | 放物線 | 上がる→下がる、または下がる→上がる |
放物線では、途中で「上がる/下がる」が切り替わる場所があります。
それがちょうど x=0(軸) の位置です。
ポイント②:xの範囲によってyの動きが変わる
たとえば y=x² の場合、
| x | y |
|---|---|
| −3 | 9 |
| −2 | 4 |
| −1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
xが0をはさんで左右対称になっていますね。
ポイント③:xの最大・最小がそのままyの最大・最小とは限らない
- 一次関数では → 直線なので常にそうだった
- y=ax²では → 放物線の形により、区間の取り方で変わる
たとえば y=x² で
- ① xが0〜3 のとき → xが大きくなるほど yも大きくなる(増加)
- ② xが−3〜0 のとき → xが大きくなるほど yは小さくなる(減少)
- ③ xが−3〜3 のとき → 0をはさんで減少→増加に変わる
ポイント④:0をはさむときの考え方
放物線は x=0を軸に左右対称 なので、
「0から離れるほどyが大きくなる(小さくなる)」ことがポイントです。
だから、
xが−3〜3 のように0をまたぐときは、
xの絶対値が大きい方を代入してyの最大を求める。
そして、
x=0のときのyが最小になる。
例題
y=2x² において、xの変域が −3≦x≦2 のとき、yの範囲を求めよ。
【解き方】
最大値を求めるには、xの絶対値が大きい方(−3)を使う:
y=2×(−3)²=18
最小値は、x=0のとき(0をまたぐため)
y=2×0²=0
✅ 答え:0≦y≦18
まとめ
- 放物線になると、xの範囲によって「増加」と「減少」が入れ替わる。
- xが0をまたぐときは、絶対値の大きいxでyが最大、x=0で最小。
- グラフが左右対称であることを意識すると、変域の考え方が整理できる。


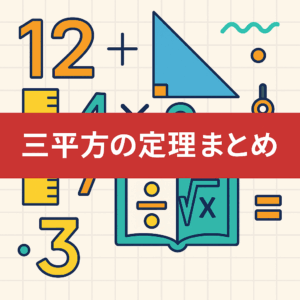
コメント