目次
導入
生徒にy=ax²の形を真っ先に見せてしまうと「曲線は無理」「絶対難しそう」というイメージがついてしまうことが多いです。
なぜその形になるのかの説明を先にしてあげることでスムーズに単元に入ることができます。
「y=ax²」と聞いて、グラフが“放物線”になるのは知っているけど、
- aが大きいとどうなるの?
- マイナスだとなんで下に開くの?
- 「比例y=ax」とどう違うの?
そんな疑問に答えるのがこの記事です。
今回は、二次関数の基本「y=ax²」の形と意味を、比例との比較でわかりやすく説明します。
ポイント①:二次関数とは何か
- 一次関数:xを1回だけ掛けている(y=ax+b)
- 二次関数:xを2回掛けている(y=ax²+bなど)
→ 「x²」が出てきた時点で、グラフはカーブする! - つまり“直線”ではなく、“放物線”になる。
- +bがないので必ず原点を通る。
ポイント②:aの符号で向きが決まる
| aの値 | グラフの向き | 特徴 |
|---|---|---|
| a > 0 | 上に開く | 谷型(U字) |
| a < 0 | 下に開く | 山型(∩字) |
x²のxには正の数・負の数のどちらをいれても必ず正の数になります。
なのでそこにかけるaの値の符号によってyの値の符号もそのまま決まります。
→ aの値がプラスなら「上に開く」、マイナスなら「下に開く」
+2と−2など絶対値が同じ値をxに代入するとyの値は必ず同じになるためy軸を軸に左右対称になります。
→ 原点を通る左右対称な形になる。
ポイント③:aの大きさでカーブの急さが変わる
| aが大きい(例:2,3) | aが小さい(例:1/2,1/3) | |
|---|---|---|
| 見た目 | 細くて急 | 広がってなだらか |
| 理由 | x²を掛けた結果、増え方が急 | x²を掛けても値が小さい |
→ y = 3x² は y = x² より急で細い
→ y = (1/2)x² は広くゆるやか
まとめ
- y=ax² は「原点を通る放物線」
- aが正:上に開く/aが負:下に開く
- aの絶対値が大きい:細く急/aの絶対値が小さい:広くゆるやか


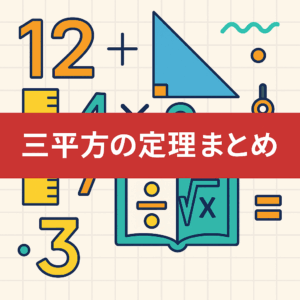
コメント