目次
導入
三平方の定理の基本は「斜辺^²=他の2辺^²の和」。
第1回でこの仕組みを確認しました。
今回はその応用として、2辺がわかっているときに斜辺を求める問題を解いていきます。
整数の組(3-4-5、5-12-13 など)を使えば、計算の流れも分かりやすくなります。
この記事は中学数学「三平方の定理」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「三平方の定理」まとめ|体系的に整理
三平方の定理で斜辺を求める流れ
直角三角形の辺を a,b,c とすると:c^2=a^2+b^2
この関係を使って、未知の c を求めます。
例題1:3cmと4cmの直角三角形の斜辺を求めよ
c^2=3^2+4^2
c^2=9+16
c^2=25
c=5
👉 3-4-5型は有名な「ピタゴラス数」です。
例題2:5cmと12cmの直角三角形の斜辺を求めよ
c^2=5^2+12^2
c^2=25+144
c^2=169
c=13
👉 こちらも整数ぴったりで出てきます。
例題3:7cmと24cmの直角三角形の斜辺を求めよ
c^2=7^2+24^2
c^2=49+576
c^2=625
c=25
ポイント
- 斜辺を求めるときは 平方和を作る → √ を取る という流れ
- 有名な整数の組(3-4-5、5-12-13、7-24-25など)は受験で頻出
- √がきれいに出なくても、そのまま答えにしてOK(例:√2, √5 など)
練習問題
- 8cm・15cm の直角三角形の斜辺を求めよ
- 9cm・40cm の直角三角形の斜辺を求めよ
- 11cm・60cm の直角三角形の斜辺を求めよ
まとめ
- 三平方の定理を使えば、斜辺がすぐに求められる
- 手順は「二乗して足す → √を取る」だけ
- 有名な整数比は暗記しておくとスピードアップ
この記事は中学数学「三平方の定理」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「三平方の定理」まとめ|体系的に整理


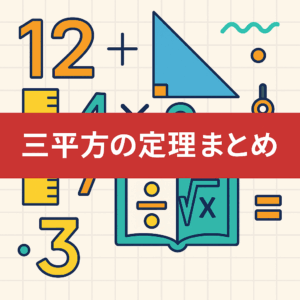
コメント