目次
導入
「三平方の定理」と聞くと難しそうに感じますが、実はとてもシンプルな法則です。
直角三角形の3つの辺について、2乗の関係が必ず成り立つというもの。
ここでいう「平方」とは「2乗」という意味。
だから「三平方」とは、3つの平方=3つの2乗の関係を指しています。
この記事は中学数学「三平方の定理」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「三平方の定理」まとめ|体系的に整理
三平方の定理とは?
直角三角形で、斜辺を c、他の2辺を a,b とすると、c^2=a^2+b^2
が成り立ちます。
これが「三平方の定理」です。
具体例で確認しよう
例:3cm・4cm・5cmの直角三角形
5^2=3^2+4^2
25=9+16
確かに成り立っていますね。
例:6cm・8cm・10cmの直角三角形
10^2=6^2+8^2
100=36+64
こちらもバッチリ!
「平方=2乗」の意味をおさえよう
- 「平方センチメートル(cm²)」は長さを2乗して面積を表す。
- 同じように「三平方」も 辺の長さを2乗して関係を表すからこの名前。
👉 “三平方の定理=3つの辺の2乗の関係” と覚えるとスッキリします。
ポイント
- 三平方の定理は「直角三角形」でしか使えない
- 「斜辺の2乗 = 他の2辺の2乗の和」
- まずは整数で成り立つ例(3-4-5、6-8-10など)で慣れる
まとめ
- 三平方の定理とは「3つの2乗の関係」
- 直角三角形の斜辺の2乗が、他の2辺の2乗の和になる
- 言葉の意味から理解すれば「公式暗記」よりもスッと頭に入る
この記事は中学数学「三平方の定理」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「三平方の定理」まとめ|体系的に整理


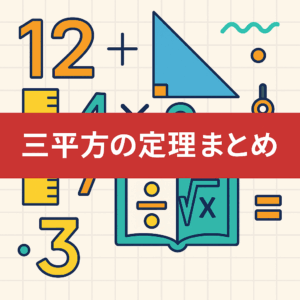
コメント