目次
導入
「式の展開」は、分配法則を繰り返すことでかけ算を整理する操作です。
中3で本格的に登場しますが、「なぜその形になるのか」を納得させること が公式暗記よりも重要です。
この記事では、式の展開を 12本の記事 に分けて体系的に整理しました。
◆展開の基本
- (a+b)(c+d) の展開はなぜ4つの項が出るのか?2項×2項の分配法則を丁寧に解説
- (a+3)(a+2) はなぜa²+5a+6になるのか?分配法則で展開の仕組みを理解しよう
- (a+3)² の展開|分配法則から理解して公式へ
- (a−3)² の展開|符号ミスをなくそう!
◆代表的な公式と使い方
- (a+3)(a−3)=a²−9|「中項が消える」差の2乗公式をマスター
- (3x−2)²=9x²−12x+4|係数つき公式をスムーズに展開
- (3x+2)(3x+4) を分配法則で展開|因数分解へつなげて理解
- (2x+3)² を置き換えて展開|係数ありもミスなく解ける方法
◆応用・発展
まとめ
- 式の展開は「分配法則の繰り返し」であり、公式はその省略形。
- まずは「なぜその形になるのか」を分配法則で理解し、その後に公式を定着させると効果的。
- 応用問題では置き換えを活用することで、計算がスムーズになる。
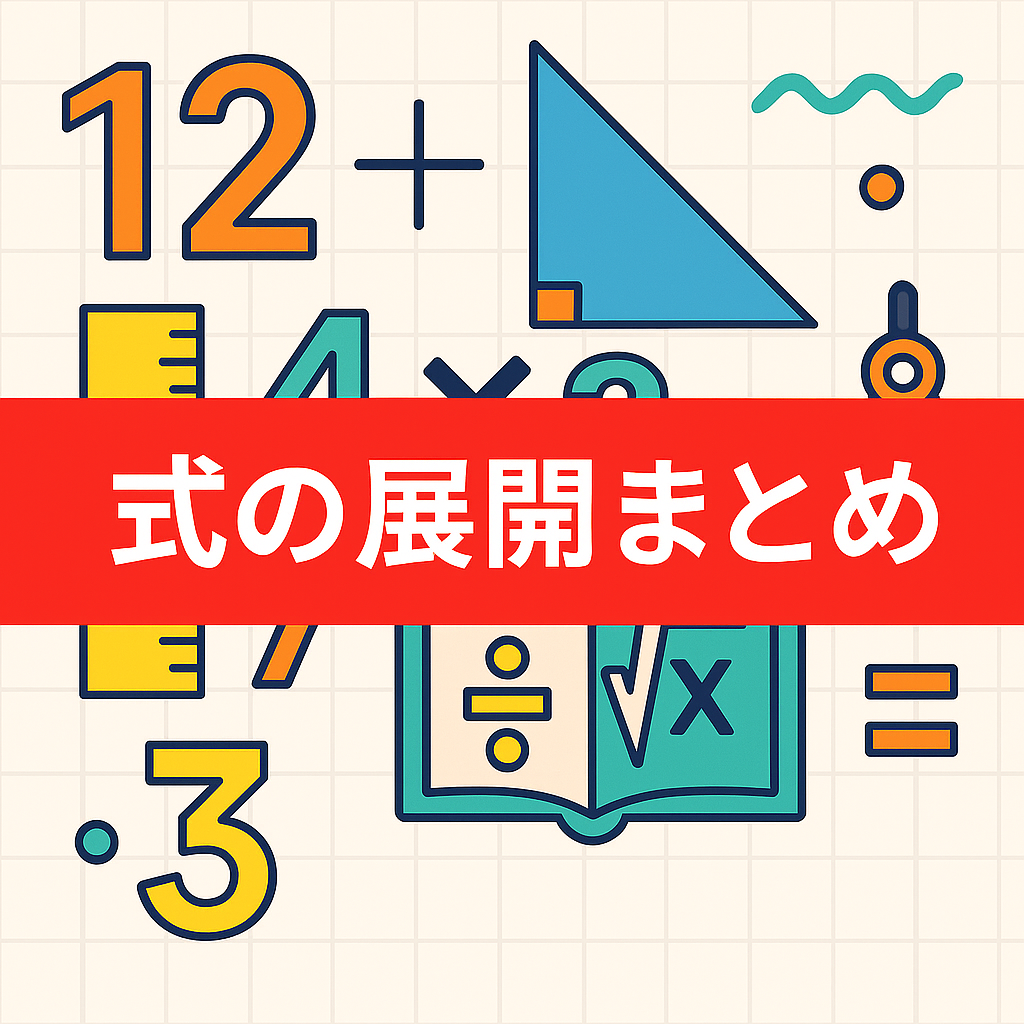

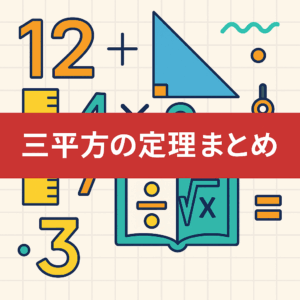
コメント