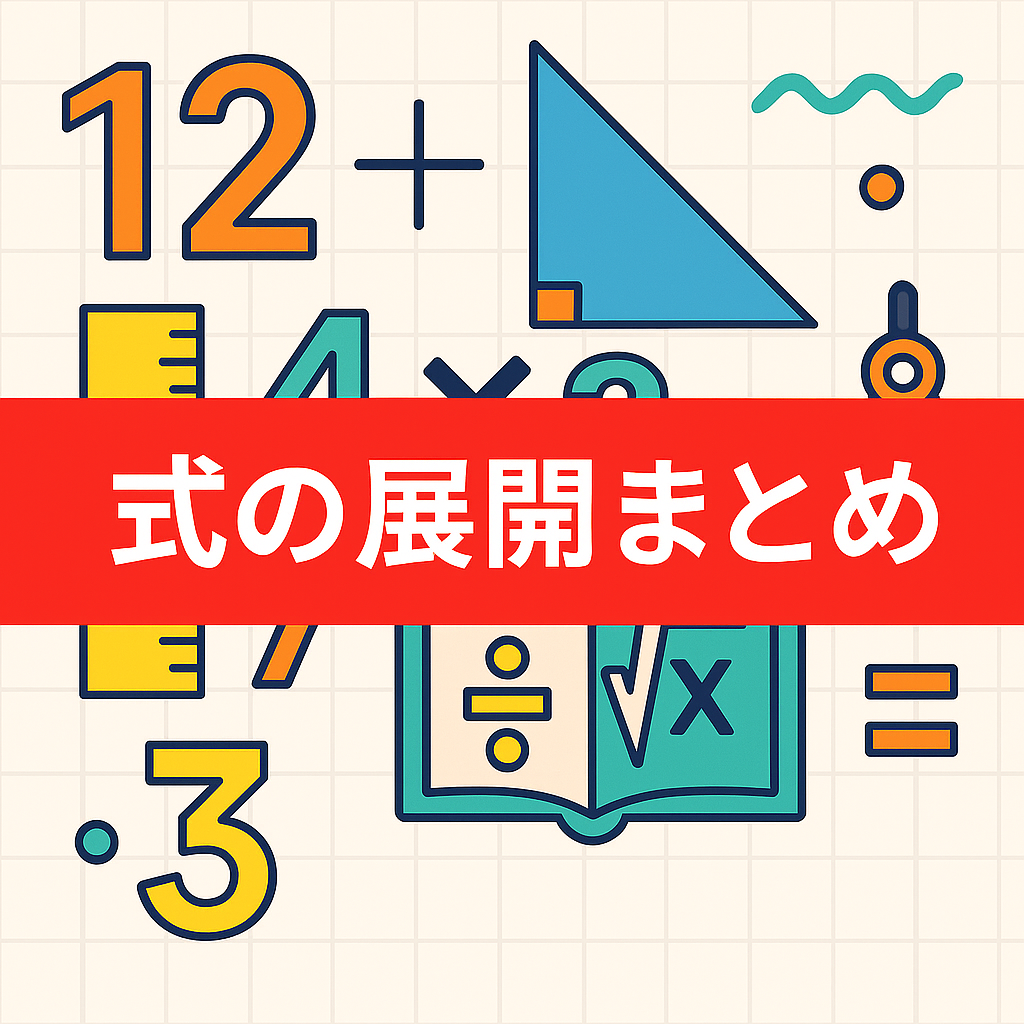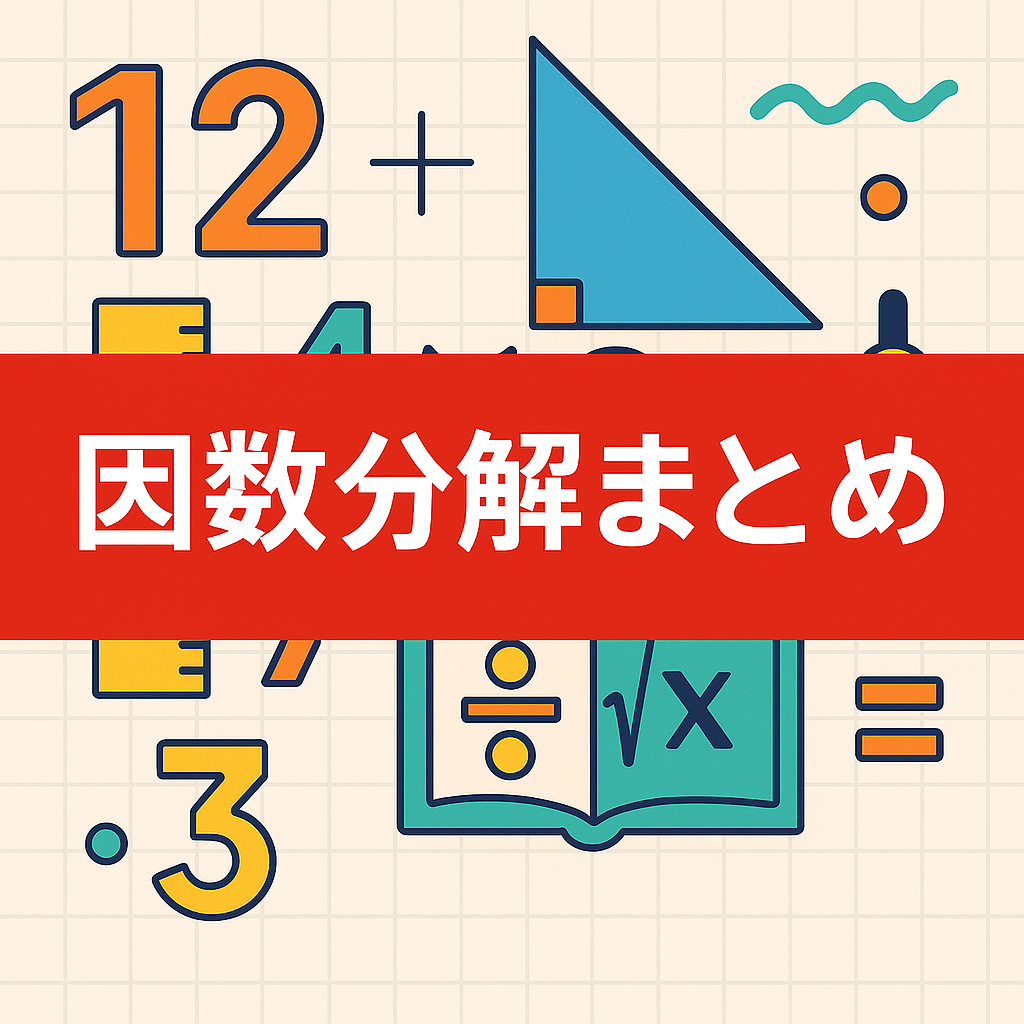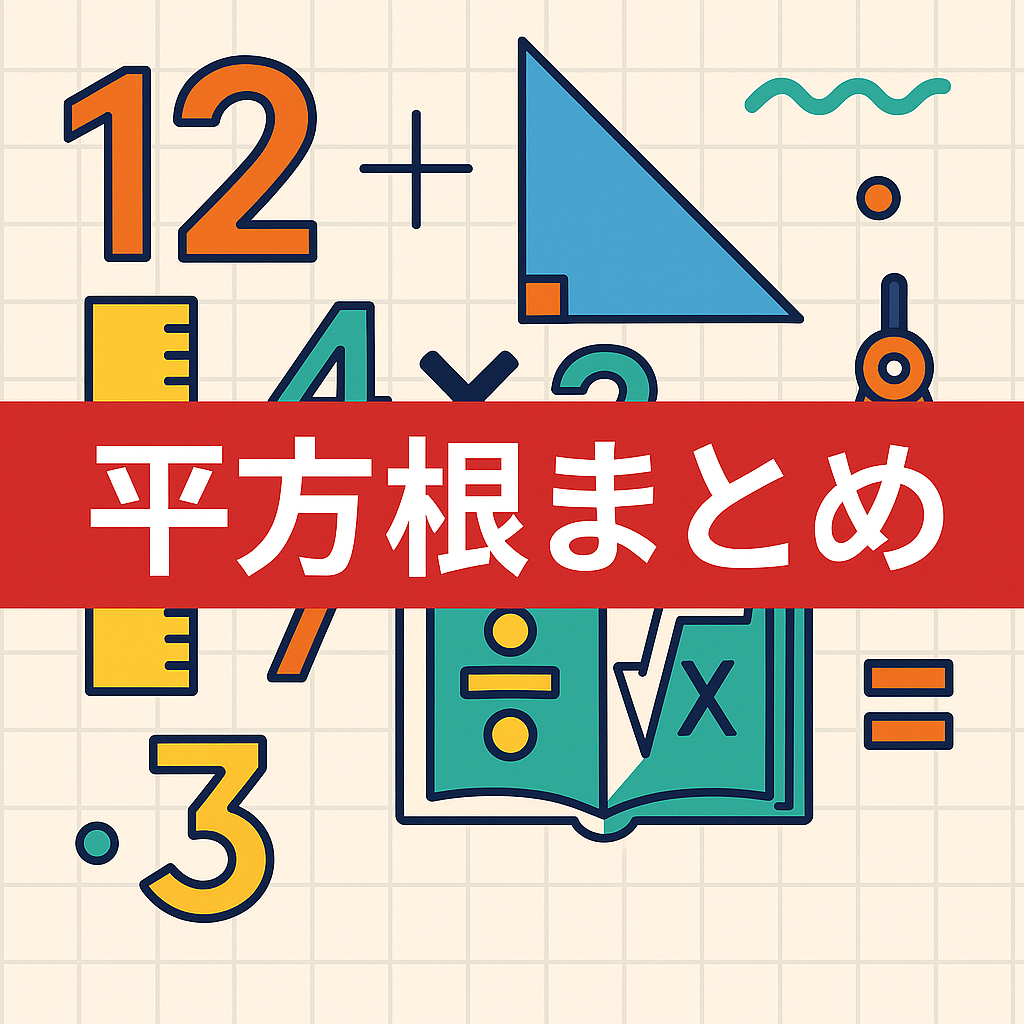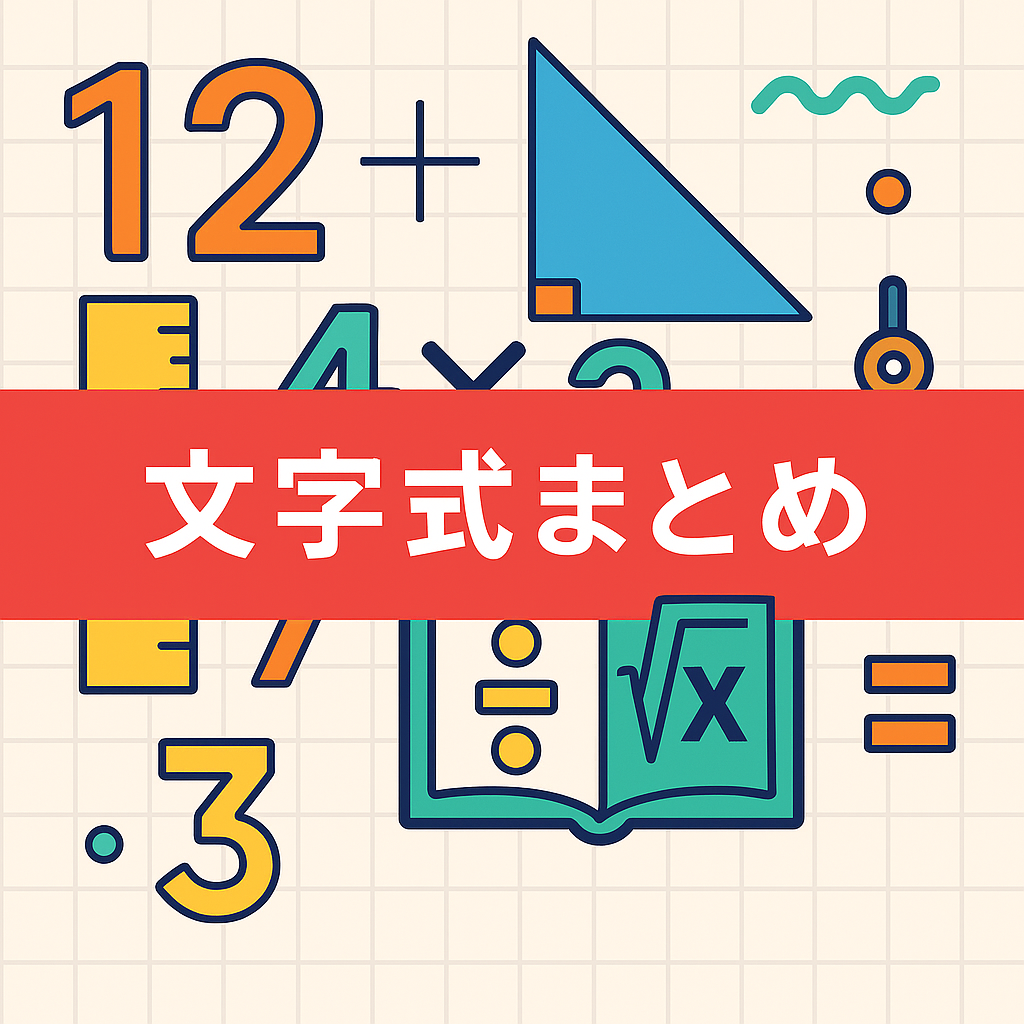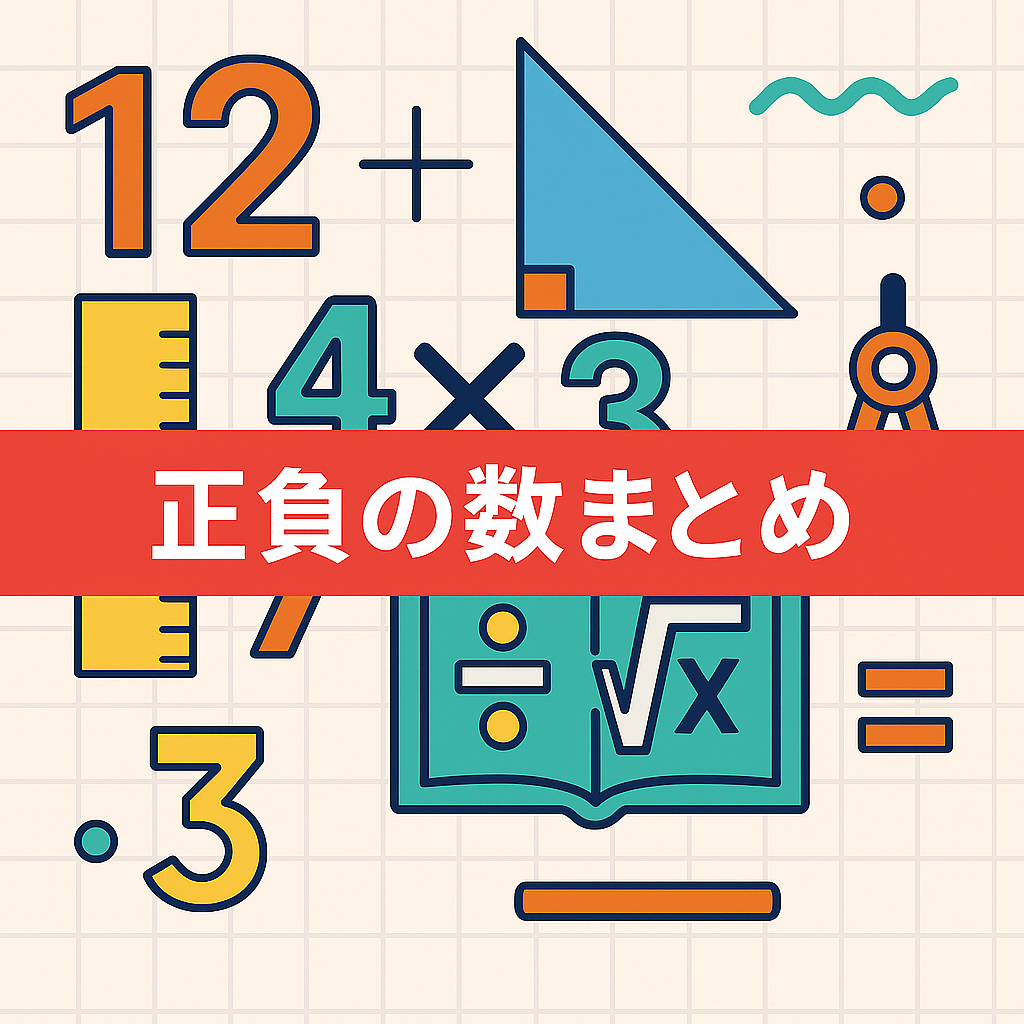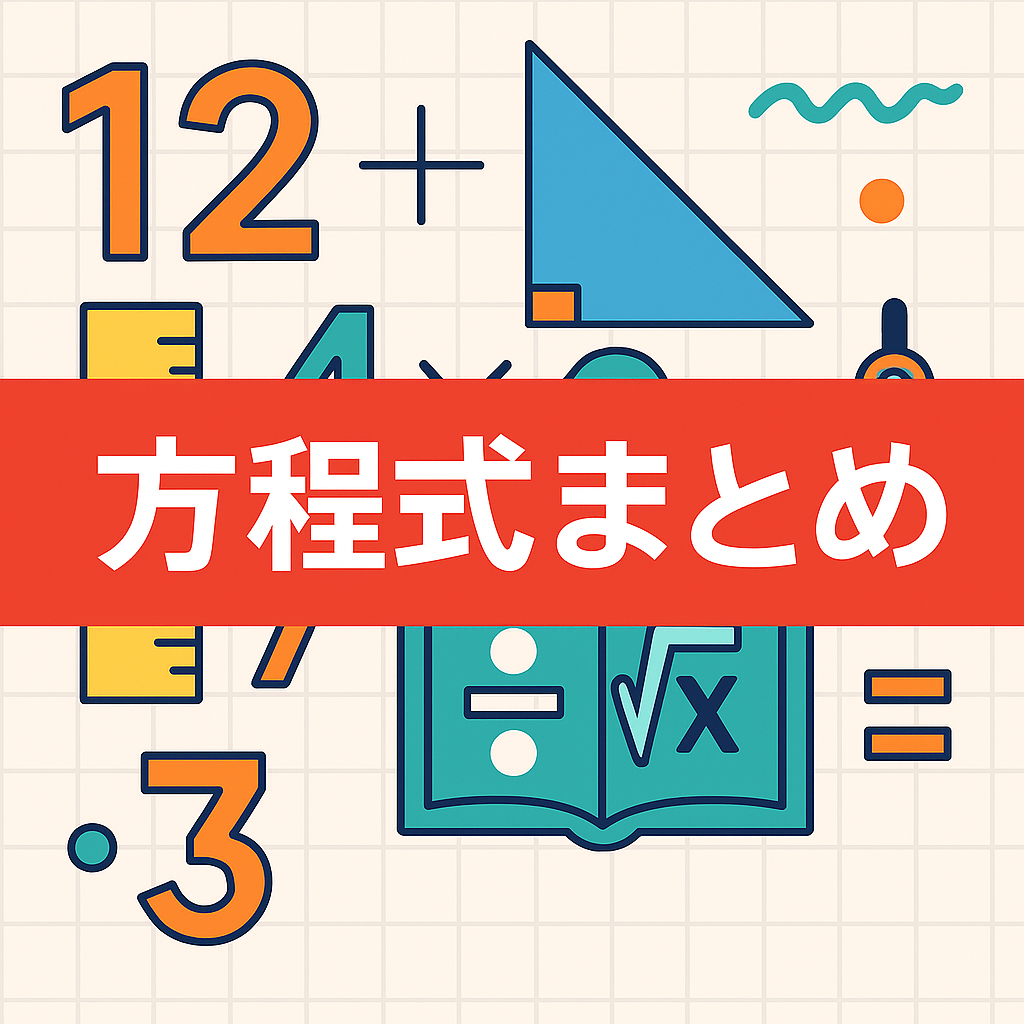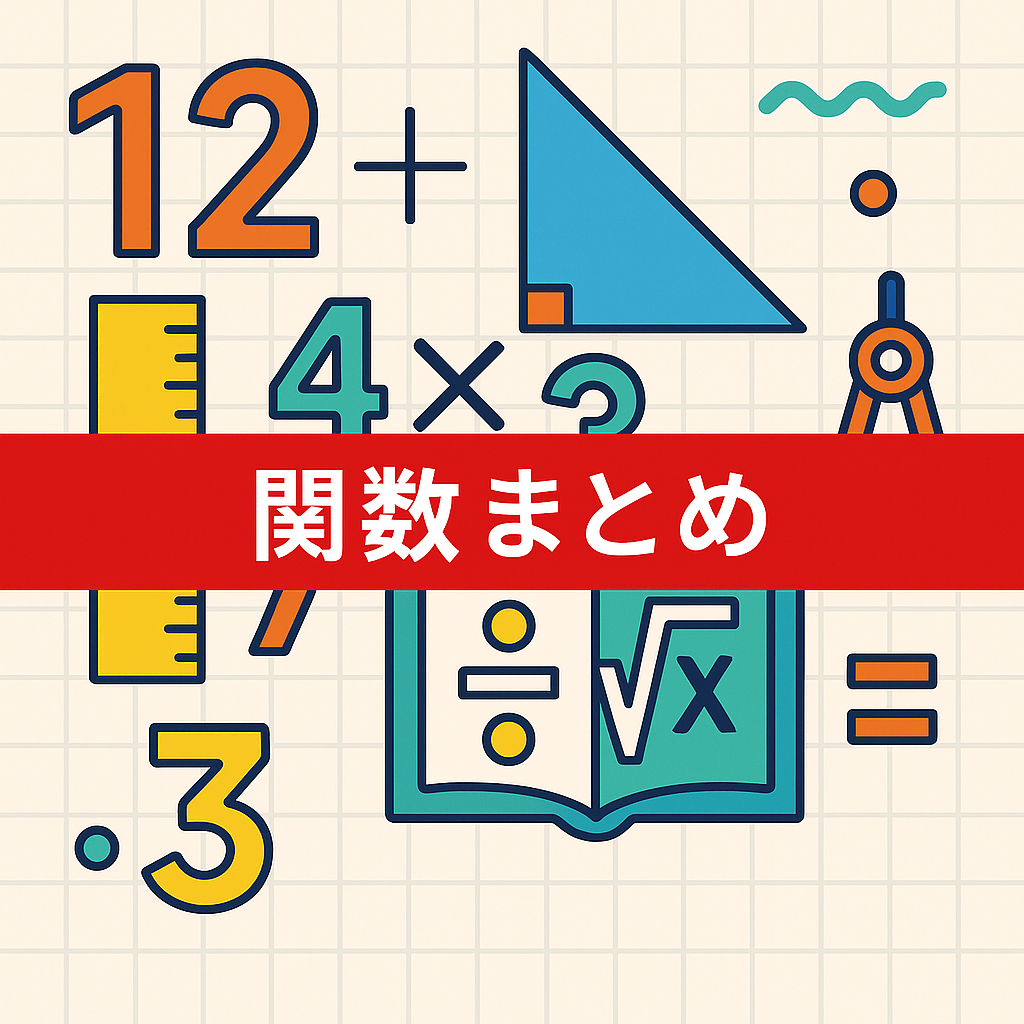-

【三平方の定理】1つの辺を求める練習問題にチャレンジ
導入 三平方の定理は「斜辺^²=他の2辺^²の和」。これを変形すれば、わからない1辺を求めることもできます。 例えば、斜辺と一方の辺がわかっていれば、残りの辺を引き算で求められるのです。 この記事は中学数学「三平方の定理」シリーズの一部です。&#... -

【三平方の定理】斜辺を求める練習問題で理解を深めよう
導入 三平方の定理の基本は「斜辺^²=他の2辺^²の和」。第1回でこの仕組みを確認しました。 今回はその応用として、2辺がわかっているときに斜辺を求める問題を解いていきます。整数の組(3-4-5、5-12-13 など)を使えば、計算の流れも分かりやすくなり... -

「三平方の定理とは?|直角三角形の3つの辺の2乗の関係をやさしく解説」
導入 「三平方の定理」と聞くと難しそうに感じますが、実はとてもシンプルな法則です。直角三角形の3つの辺について、2乗の関係が必ず成り立つというもの。 ここでいう「平方」とは「2乗」という意味。だから「三平方」とは、3つの平方=3つの2乗の関係を... -

【中3数学】式の展開まとめ|分配法則から公式・応用まで12記事で体系的に整理
導入 「式の展開」は、分配法則を繰り返すことでかけ算を整理する操作です。中3で本格的に登場しますが、「なぜその形になるのか」を納得させること が公式暗記よりも重要です。 この記事では、式の展開を 12本の記事 に分けて体系的に整理... -

【中3数学】因数分解まとめ|基本パターンから応用まで12記事で体系的に整理
導入 中3で学ぶ「因数分解」は、展開の逆の操作。パターンを覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を理解すること が、公式の暗記よりも大切です。 この記事では、因数分解を 12本の記事 に分けて体系的に整理しました。 ◆因数分解の基本... -

【中3数学】平方根まとめ|意味・計算・性質を11記事で体系的に整理
導入 中3で登場する「平方根」は、多くの生徒が「ルートって何?」と混乱する単元です。平方根の意味・計算ルール・性質をしっかり押さえることが、二次方程式や関数へとつながります。 この記事では、平方根を 11本の記事 に分けて体系的に整理... -

【中1数学】文字式まとめ|導入から計算・文章題まで10記事で体系的に整理
導入 中1数学で学ぶ「文字式」は、算数から数学への橋渡しとなる重要な単元です。「文字を数の代わりに使う意味」「計算ルール」「文章題への応用」など、ここで理解しておくことが後の方程式・関数に直結します。 この記事では、文字式を10本の記事に分け... -

【中1数学】正負の数まとめ|符号のルールから計算・数直線まで体系的に整理
導入 中学最初に学ぶ「正負の数」は、多くの生徒がつまずく単元です。「符号のルール」「数直線の使い方」「かっこの役割」など、理解すべきポイントが一気に出てきます。 この記事では、正負の数を7本の記事 に分けて整理しました。保護者や先生が教... -

【中学数学】方程式の完全ガイド|中1〜中3の33記事を体系的に整理
導入 中学数学で学ぶ「方程式」は、学年が進むごとに中1:一次方程式 → 中2:連立方程式 → 中3:二次方程式と発展していきます。 この記事では、すでに公開済みの記事を 全33本 一覧化し、体系的に整理しました。学習の順番を明確にしたことで、先生・保護... -

中学数学「関数」まとめ|比例・反比例・一次関数を体系的に整理
導入 関数は、中学3年間を通して少しずつ発展していく「数どうしの関係をとらえる」分野です。中1では「比例・反比例」を学び、中2で「一次関数」へ広がり、中3では「二次関数」へと続いていきます。一見バラバラに見えるこれらの内容は、実はすべて「xとy...