導入
「方程式の文章題、どうやって式を立てればいいの?」
こんなふうに悩む生徒はとても多いです。
実はコツはたった1つ。
それは「等しいものを見つけて=で結ぶ」ことです。
この記事では文章のどこを読んでどう式を作るか、
中学生でもスッキリ理解できるように解説します。
二次方程式の文章題では、まず「式を立てる」ことが最大のハードルです。
でも実はコツがあります。
それは、「等しいもの」を見つけて=で結ぶという考え方です。
この記事では、文章のどこを読んで、どう式にするのか、その基本の型を丁寧に説明します。
この記事は中学数学「方程式」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「方程式」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
文章題で大切なこと
文章題では、“〜は〜”という表現が出てきます。
これは「左辺=右辺」の合図です!
たとえば:
「Aの面積はBの面積の2倍です」 → A = 2B
「代金の合計は1500円です」 → 合計 = 1500
このように、「等しいもの」を見つけて=でつなぐのが基本です。
例題1:数の和と積の関係
「2つの数の和が10で、積が21になるときの数を求めよ」
→ 2つの数を a, b とすると:
a + b = 10(和)
a * b = 21(積)1つを x とすれば、もう1つは 10 − x:
x(10 − x) = 21展開して:
x² − 10x + 21 = 0→ 二次方程式ができた!
例題2:入場料と人数の問題
「子ども1人300円、大人1人500円。全部で20人いて、合計料金は7800円。子どもは何人?」
→ 子どもの人数を x とすると、大人は 20 − x 人
代金の合計は:
300x + 500(20 − x) = 7800整理して:
300x + 10000 − 500x = 7800
→ −200x = −2200
→ x = 11→ 子どもは11人!
ポイント
- 「〜は〜」は「=」の合図!
- 「式を立てる=等しいものを見つける」
- 等しい数量の構造を見抜く練習が大切
練習問題
問題1:数の関係から式を立てよう
2つの数の和が12、積が32
→ 1つを x として式を作ろう問題2:料金の合計で式を立てよう
大人1人600円、子ども1人400円。全部で30人、合計は14800円。
→ 子どもを x として式を立てようまとめ
- 文章題ではまず「=で結ぶ」発想が重要
- 「〜は〜」に注目して等しい数量を見つけよう
- あとはそれを式にすればOK!
この記事は中学数学「方程式」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「方程式」まとめ|中1〜中3を体系的に整理


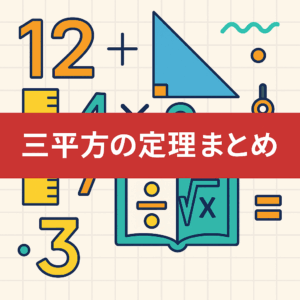
コメント