目次
導入
中2までの確率では「有利な事象の数 ÷ 全事象の数」で基本を学びました。
中3になると、もう一歩進んで 余事象(よじしょう) や 『少なくとも1回は〜』の確率 を扱います。
「全部を数えるのが大変!」というときに役立つ便利な考え方です。
この記事では、余事象と少なくとも1回はの考え方を例題とともに整理します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
余事象とは?
- ある事象が「起こらない」こと。
- 確率の性質:
ある事象の確率+その余事象の確率=1ある事象の確率+その余事象の確率=1
👉 「起こる」か「起こらない」かのどちらかしかないので、2つを足せば必ず1になる。
例
サイコロを1回投げるとき、
- 「1が出る確率」=1/6
- 「1が出ない確率」=5/6
両方を足すと 1。これが余事象の考え方。
『少なくとも1回は』の確率
「少なくとも1回は〜が起こる」=「1回も起こらない場合を除いた残り」
例1:コインを2回投げて、少なくとも1回は表が出る確率
- 全事象=4通り(表表, 表裏, 裏表, 裏裏)
- 「表が1回も出ない」=裏裏の1通り
- よって、少なくとも1回表= 1 − 1/4 = 3/4
👉 数え上げより「余事象を使う」方が楽になる。
例2:サイコロを3回投げて、少なくとも1回は6が出る確率
- 「6が1回も出ない」= {1,2,3,4,5}^3 = 5³=125通り
- 全事象=6³=216通り
- 確率=1 − 125/216 = 91/216
👉 『少なくとも1回』は「全部の確率 − 出ない確率」で解ける。
ポイント整理
- 余事象:ある事象が起こらない場合
- 『少なくとも1回』:1回も起こらない場合を除いたもの
- 数え上げが大変なときは「余事象」を使えばスッキリ解ける
まとめ
- 余事象を使えば「起こる/起こらない」で確率を簡単に計算できる
- 少なくとも1回は=「全部 − 出ない場合」で求める
- サイコロやコインの複数回試行では必須のテクニック
この考え方を理解すると、確率の応用問題が一気に解きやすくなります。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ


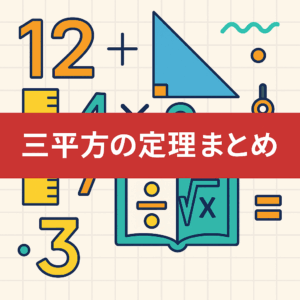
コメント