導入
因数分解の中でも、最初に絶対おさえておきたいのが 「共通因数でくくる」 パターンです。
たとえば、a(x−y)+b(x−y) のように、同じかたまり (x−y) が何度も出てくるときは、
それを“ひとまとまり”として前に出すことで、式全体をすっきり整理できます。
これは 「たし算の中にかけ算を見抜く」 操作でもあり、
展開(分配法則)の逆の動きをしていることに気づけると理解が一気に深まります。
この記事では、共通因数でくくる基本型の考え方と、
実際の例題を使った教え方・確認のポイントを解説します。
この記事は中学数学「因数分解」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「因数分解」まとめ|体系的に整理
例題:a(x−y)+b(x−y) を因数分解せよ
ステップ①:共通するかたまりを見つける
両方の項に (x−y) が共通していることに注目します。
共通部分が文字やかっこを含んでいても「まるごと一つのかたまり」として扱えるのがポイント。
ステップ②:共通因数でくくる
a(x−y)+b(x−y)
= (a+b)(x−y)
くくったあとは、( ) を必ず2つ書き、
「前のかっこが“まとめたもの”、後ろのかっこが“共通部分”」になるよう意識させましょう。
ポイント
この単元では「展開の逆」を体感させることが重要です。
たとえば授業や家庭学習で、最初に「(a+b)(x−y)を展開したらどうなる?」と聞き、
元の形に戻ることを確認すると、くくる動作の意味が一瞬で理解できます。
また、生徒が「xが共通している」と部分的に見てしまうことが多いので、
“かっこも含めて一つのかたまり” という指導を意識して伝えると定着が早くなります。
まとめ
- 共通因数(かたまり)を見つけたら前に出して ( ) を使う
- 因数分解は「たし算の中にかけ算を見抜く」操作
- 展開して元に戻ることを必ず確認しよう
この記事は中学数学「因数分解」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「因数分解」まとめ|体系的に整理


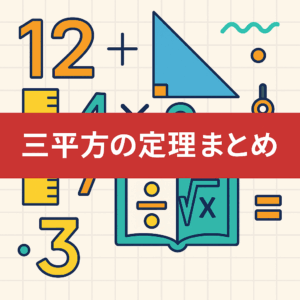
コメント