目次
導入
「クラス全員の身長を調べたいけど、1人ずつ測るのは大変」
「全国の有権者の意見を知りたいけど、全員にアンケートはできない」
こんなときに使われるのが 標本調査 です。
中3の「データの活用」では、母集団(調べたい全体)と標本(調べる一部)の考え方を学び、限られた調査から全体を推測する力を身につけます。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
母集団(ぼしゅうだん)とは?
- 調べたい対象の「全体」
- 例:全国の中学生、クラス全員の身長、全ての工場製品
👉 本当は母集団全員を調べるのが理想(これを「悉皆調査(しっかいちょうさ)」という)が、現実的には難しい。
標本(ひょうほん)とは?
- 母集団から取り出した「一部のデータ」
- 標本を調べて、母集団全体の傾向を推測する
- 例:クラス全員の平均身長を調べる代わりに、5人の身長を調べて平均を出す
無作為抽出(むさくいちゅうしゅつ)の大切さ
- 標本は ランダムに選ぶこと が重要
- 偏った取り方をすると正しい推測ができない
例
- テストの点数を「成績上位だけ」から取れば、平均は高めに出る
- 「体育部だけ」から取れば、身長は高めに出る
👉 公平に調べるために「無作為(ランダム)に抽出」する必要がある。
実生活での標本調査
- 選挙の出口調査:投票所を出た人にランダムに聞いて全体を推測
- 世論調査:無作為に選んだ電話番号にアンケート
- 品質検査:製品の一部を抜き取り、全体の品質を判断
まとめ
- 母集団=調べたい全体
- 標本=調べる一部
- 無作為抽出で偏りをなくすことが大切
- 標本調査は現実の社会で広く使われている
中3の標本調査は「統計的なものの見方」の入り口です。ニュースや社会問題に触れるときにも、とても役立つ考え方です。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ


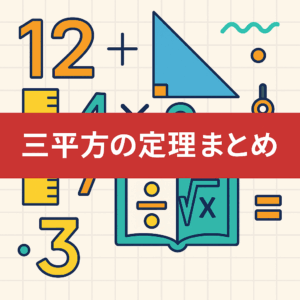
コメント