目次
導入
「(3x+2)(3x+4)のような式は、どうやって展開すればいいの?」
そんな疑問をもつ生徒に、最もわかりやすく教えられるのが「分配法則」の考え方です。
この記事では、分配法則を使って展開する流れをステップごとに整理し、
さらに展開と因数分解の関係もあわせて理解できるように解説します。
教える立場でも使いやすい、授業・教材向けの構成です。
この記事は中学数学「式の展開」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「式の展開」まとめ|体系的に整理
例題:(3x+2)(3x+4) を展開せよ
まず、分配法則に従って計算します。
(3x+2)(3x+4)
= 3x×3x + 3x×4 + 2×3x + 2×4
= 9x² + 12x + 6x + 8
= 9x² + 18x + 8→ 係数があっても、分配法則さえ正しく使えれば簡単!
たまには逆:分配法則で作られた式を因数分解してみよう
以下の式がどんな2つのかっこの積から来たのかを考えてみましょう。
9x² + 18x + 8→ 因数分解すると?
(3x+2)(3x+4)展開と逆の操作ができれば、理解が深まります!
ポイント
- まずは1つ目のかっこの各項を、2つ目のかっこの各項に順に掛ける
- 中項(xの項)をきれいにまとめる
- 確認として因数分解にも挑戦してみよう
練習問題
問題1:
(2x+5)(2x+1) を展開せよ。
問題2:
(4a+3)(4a+2) を展開せよ。
問題3:
次の式を因数分解せよ: 16a²+20a+6
まとめ
- 展開の基本は分配法則!公式に見えなくても手順で対応
- 中項を正しく計算することが鍵
- 展開と因数分解は表裏一体。両方できるようにしておこう
この記事は中学数学「式の展開」シリーズの一部です。
👉 流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「式の展開」まとめ|体系的に整理


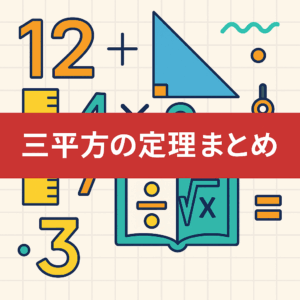
コメント