目次
導入
中2で学ぶ「データの活用」では、確率・散らばり・箱ひげ図 などを学んできました。
テストや教科書の中だけの知識にとどめるのはもったいない!
これらは実生活やニュースの中で「ものごとを正しく理解する力」につながります。
この記事では、確率とデータの考え方がどんな場面で活きるのかを整理します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
ニュースでのデータ解釈
- 平均値と中央値の違いに注意
→ 給与や家計のニュースは「中央値」の方が生活実感に近いことが多い - 箱ひげ図やグラフで「ばらつき」や「偏り」を読み取ると誤解が少ない
スポーツの確率
- 野球やサッカーで「勝率○割」と出るのは確率の応用
- サイコロの目と同じで、全事象に対して有利な事象がどれだけあるか で考える
- 長いシーズンを通して「確率に近い結果」が見えてくる
天気予報の確率
- 「降水確率40%」=100回同じ条件なら40回は雨が降る見込み
- 「必ず降る」「必ず降らない」ではなく、可能性を数で表している
ガチャやくじ引きの確率
- ゲームのガチャ「星5が出る確率3%」
- 計算上は100回引いても出ないこともあるし、1回で出ることもある
- 確率はあくまで長期的に見たときの割合
データ活用のまとめ
- 平均・中央値・最頻値 → 目的によって使い分ける
- グラフ → 「何を伝えたいか」に合わせて種類を選ぶ
- 散らばり → 安定性や偏りを把握する
- 確率 → 不確実なものを数で表す
👉 どれも「正しく情報を読み取る力」につながり、生活や社会で役立ちます。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ

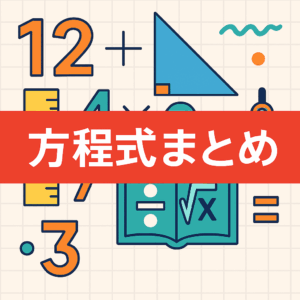
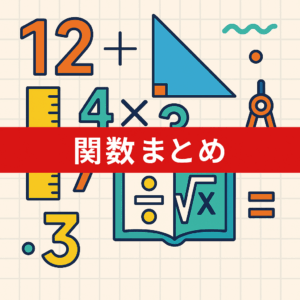
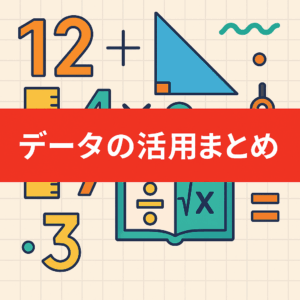

コメント