導入
中1で学んだ「範囲(最大-最小)」はシンプルで便利ですが、外れ値(極端に大きい値や小さい値)があると、実態を正しく表せないことがあります。
そこで中2では、より安定した「散らばりの指標」として 四分位範囲 を学びます。そして、この考えをグラフ化したのが 箱ひげ図 です。
この記事では、四分位数・四分位範囲・箱ひげ図を順番に解説します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
四分位数とは?
データを小さい順に並べ、4つに分けたときの区切りの値。
- 第一四分位数(Q1):下位25%の区切り
- 第二四分位数(Q2):中央値(全体の真ん中)
- 第三四分位数(Q3):上位25%の区切り
👉 データを「4つのブロック」に分けるイメージ。
四分位範囲(IQR)とは?
四分位範囲=Q3 − Q1
- データの「真ん中50%」の広がりを表す
- 外れ値の影響を受けにくい
- 平均や範囲と組み合わせると、より正確にデータの特徴をとらえられる
箱ひげ図とは?
四分位数と範囲を1本の図にまとめたもの。
- 箱の左端=Q1
- 箱の右端=Q3
- 箱の中央の線=Q2(中央値)
- ひげ=最小値と最大値
👉 一目で「データの散らばり」「偏り」「中央値の位置」がわかる。
箱ひげ図で読み取れること
- 箱が狭い → データが集中している
- 箱が広い → データがばらついている
- 中央線が箱の中心からずれている → データが偏っている
- ひげの長さ → 全体の散らばりの様子
まとめ
- 四分位数=データを4分割する区切り(Q1, Q2, Q3)
- 四分位範囲=Q3 − Q1、データの真ん中50%の広がり
- 箱ひげ図=四分位数と範囲をまとめたグラフ
範囲だけでは見えなかった「安定した散らばり」をつかむことができます。箱ひげ図は入試問題や実生活のデータ解釈でもよく出てくるので、早めに慣れておきましょう。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ

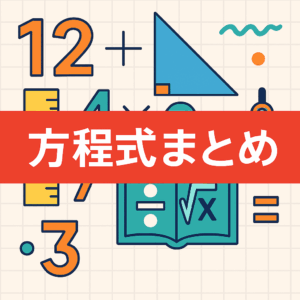
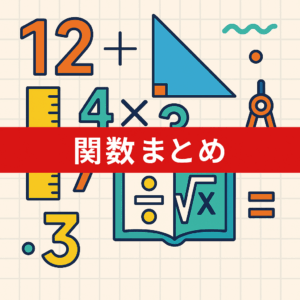
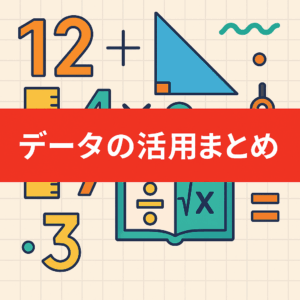

コメント