導入
中1の「データの活用」では、平均・中央値・最頻値やグラフ、散らばりなどを学びました。
ここまでで「計算できる」ようになることはもちろん大切ですが、それ以上に重要なのは「実際の生活でどう役立つか」を考えることです。
この記事では、これまで学んだ代表値やグラフを「実生活やニュース」に結びつけて整理します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
平均値とニュースの見方
ニュースや学校の成績発表では「平均」がよく使われます。
ただし、平均値は外れ値に大きく影響されるので注意が必要です。
例
- ある会社の給料の平均が「500万円」でも、一部の高収入の人が押し上げているかもしれない。
- 実際の感覚に近いのは「中央値」になることも多い。
👉 平均だけで判断せず、他の代表値も意識するクセをつけよう。
中央値で「実感」を知る
中央値は「真ん中の人」を表すので、生活実感に近い数値を知るときに有効です。
例
- 家計調査や給与統計では「中央値」がよく使われる。
- 学力テストで「自分がどのあたりか」を判断するのにも役立つ。
最頻値で人気や流行を知る
最頻値は「一番多いもの」を示すので、流行や人気を知るのに適しています。
例
- ファッションで一番売れているサイズ
- コンビニでよく売れている商品
- アンケートで一番多かった答え
👉 「みんなが選んでいるもの」を知るときは最頻値。
グラフで伝える力を身につける
グラフは「伝える道具」。
- 円グラフ=割合の比較
- 棒グラフ=量の比較
- 折れ線グラフ=変化の比較
ただし、グラフの種類を間違えると「伝わりにくい」「誤解を招く」こともあるので要注意。
散らばりで「安定性」を知る
平均が同じでも、範囲やヒストグラムで「ばらつき」を見れば違いがわかる。
例
- クラスの平均点が同じでも、範囲が狭ければ安定している。
- 範囲が広いと、点数に大きな差があることがわかる。
まとめ
- 平均・中央値・最頻値:目的に応じて使い分ける
- グラフ:伝えたい内容に合わせて選ぶ
- 散らばり:平均だけでは見えないデータの特徴を知る
「データの活用」は、テストのためだけでなくニュース・買い物・日常生活のあらゆる場面で役立ちます。
数学を「生活の道具」として使えるようになることが、この単元のゴールです。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ
次に読むならこちらもおすすめです。
🔗 中1方程式の教え方まとめ|教材シリーズはこちら

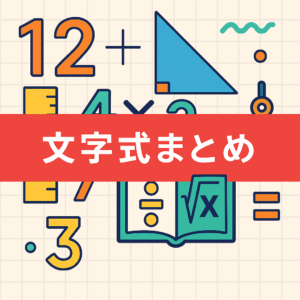
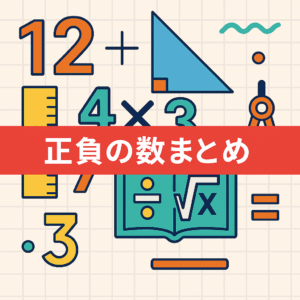
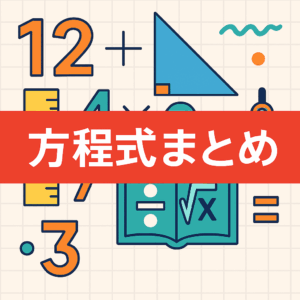
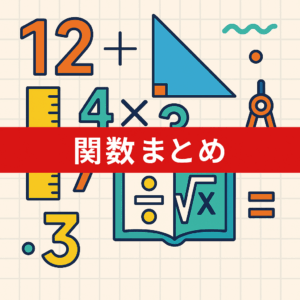
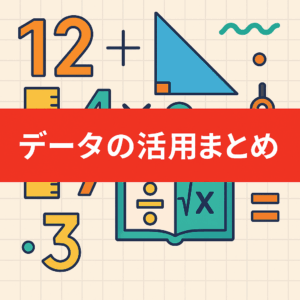

コメント