導入
中学1年の数学「データの活用」では、データが多いときにどう整理するかを学びます。
数個のデータなら平均や中央値をすぐに出せますが、何十人ものテスト結果や身長データがあると、見づらくなりますよね。
そこで使うのが「度数分布表」と「ヒストグラム」です。この記事では、データの整理の仕方と、それをグラフに表す方法をわかりやすく解説します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
度数分布表とは?
- 定義:データを「区間」に分け、それぞれに何個あるかを数えた表。
- メリット:大量のデータを見やすく整理できる。
- キーワード:
- 区間(階級)
- 度数(データの個数)
- 相対度数(全体に対する割合)
例
テストの点数(100点満点、40人分)を10点ごとに分ける。
| 階級(点数) | 度数(人数) |
|---|---|
| 40~49 | 3人 |
| 50~59 | 8人 |
| 60~69 | 12人 |
| 70~79 | 10人 |
| 80~89 | 5人 |
| 90~100 | 2人 |
→ これが「度数分布表」。
ヒストグラムとは?
- 定義:度数分布表を棒グラフにしたもの。
- 特徴:棒と棒の間にすき間をあけず、連続したデータの分布を表す。
- 読み取りのポイント:
- 棒の高さ=その区間の人数
- 山の位置や形でデータの傾向がわかる
👉 「どの点数帯が一番多いか」「データが左右どちらに偏っているか」が一目でわかる。
散らばりとのつながり
ヒストグラムを使うと、データの「まとまり具合」や「ばらつき」が見えてきます。
- 棒が狭い範囲に集中 → データがまとまっている
- 棒が広い範囲に分散 → データがばらついている
この考え方が次の単元「散らばり」を学ぶステップになります。
まとめ
- 度数分布表=大量のデータを区間ごとにまとめた表
- ヒストグラム=度数分布表をグラフ化したもの
- 活用の意義=データの傾向や散らばりを直感的につかめる
代表値だけでは見えない「全体の形」をとらえるのが、度数分布とヒストグラムの役割です。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ
次に読むならこちらもおすすめです。
🔗 中1方程式の教え方まとめ|教材シリーズはこちら

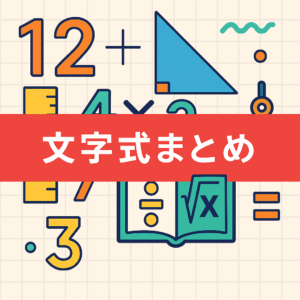
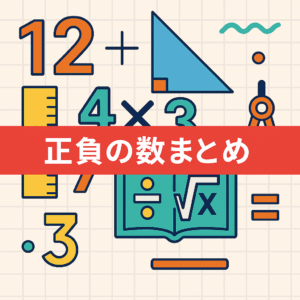
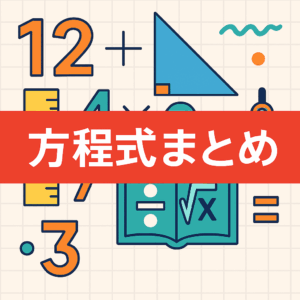
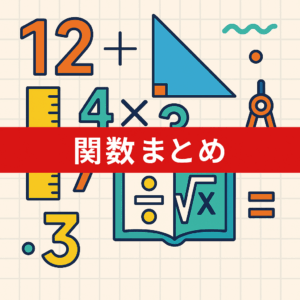
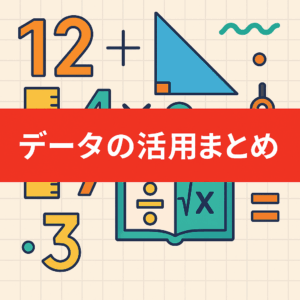

コメント