導入
中学1年生の数学「データの活用」では、アンケートや調査の結果をグラフにまとめて考える練習をします。
グラフにはいくつか種類がありますが、「どんなときにどのグラフを使うか」を理解していないと正しく情報を伝えられません。
この記事では、中1で学ぶ代表的な3種類のグラフ──円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフ──の特徴と使い分けを解説します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
円グラフ
- 特徴:全体を「100%」として、各部分の割合を扇形で表す。
- メリット:割合の比較が直感的にわかりやすい。
- デメリット:データの数が多すぎると見にくい。
例
クラス40人の好きな果物の割合を表すとき、「いちご 40%、りんご 30%、バナナ 20%、その他 10%」など。
棒グラフ
- 特徴:データを長さのちがう棒で表す。
- メリット:大きさの比較がしやすい。
- デメリット:時間の変化を表すのにはあまり向いていない。
例
「クラスごとの人数」「教科ごとの得点」などを比較するときに使う。
折れ線グラフ
- 特徴:点を線で結び、時間の経過や変化の様子を表す。
- メリット:増加・減少の傾向がわかりやすい。
- デメリット:単発の比較には不向き。
例
「1年間の気温の変化」「テストの点数の推移」などに使う。
3つの使い分けのまとめ
- 割合を比べたいとき → 円グラフ
- 量を比べたいとき → 棒グラフ
- 変化を見たいとき → 折れ線グラフ
同じデータでも、グラフを変えると印象や伝わり方が違います。ここを意識することが「数学の伝える力」を身につける第一歩です。
まとめ
中1で学ぶグラフは主に3種類。
- 円グラフ=割合を伝える
- 棒グラフ=量を比較する
- 折れ線グラフ=変化を追う
「どのグラフを選ぶか」は数学だけでなく、社会・理科・国語の発表やレポートにも役立ちます。自分でグラフを作るときは、目的に合ったものを選びましょう。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ
次に読むならこちらもおすすめです。
🔗 中1方程式の教え方まとめ|教材シリーズはこちら

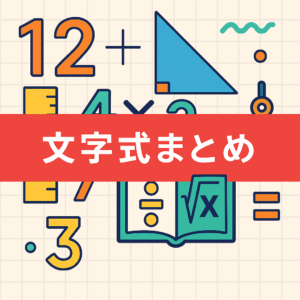
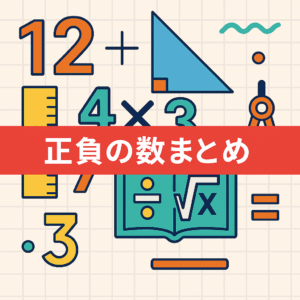
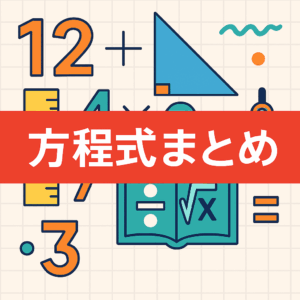
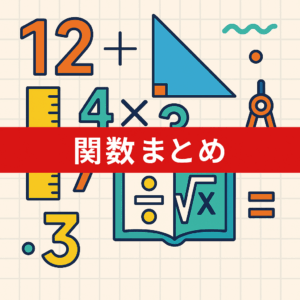
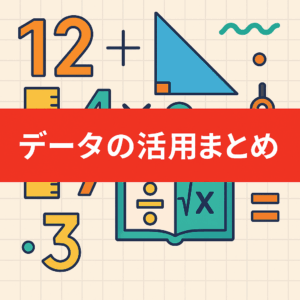

コメント