導入
「データの活用」は、中学1年〜3年まで3年間かけて少しずつ発展していく単元です。
中1ではデータを「整理して見る」こと、
中2では「確率とデータを結びつけて考える」こと、
中3では「全体を推測する」力へと発展していきます。
他の単元と比べても、実生活とのつながりがとても強いのが特徴です。
ニュース・スポーツ・アンケート・天気予報など、身近な例で考えられるため、
「数学が現実とどう関係しているか」を実感できる分野です。
この記事では、3年間の「データの活用」を体系的に整理し、
学年ごとにどんな考え方を学ぶのかをまとめました。
それぞれの記事に進む前に、まず全体像をつかんでおきましょう。
中1 データの活用
① 代表値(平均・中央値・最頻値)
代表値の基本と使い分け。外れ値に注意!
② グラフの種類と使い分け
円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフの特徴。
③ 度数分布表とヒストグラム
大量のデータを整理する方法。
④ 散らばり(範囲・四分位範囲の入口)
平均だけでは見えないデータの広がり。
⑤ 実生活での活用まとめ
ニュースや調査にどうつながるか。
中2 データの活用
① 確率の基本
確率=有利な事象 ÷ 全事象。
② 樹形図と表で整理する確率
数え落としを防ぐ方法。
③ 四分位範囲と箱ひげ図
中央値・四分位数・箱ひげ図の読み取り。
④ 確率とデータのまとめ
ニュース・スポーツ・天気・ガチャと結びつける。
中3 データの活用
① 標本調査(母集団と標本)
全体を調べられないときの調査方法。
② 確率の発展①:余事象・少なくとも1回は
「1回も起こらない確率」を使って計算。
③ 確率の発展②:組合せを使った確率
順序を考えない場合の数え方。
④ 実社会での活用まとめ
ニュースや調査・ゲームにどう活かすか。
まとめ
中学3年間の「データの活用」を通じて、
- データを整理して代表値や散らばりを読み取る
- 確率で偶然を数で表す
- 標本調査から全体を推測する
という 「情報を扱う数学の力」 を養えます。
実生活にも直結する分野なので、この記事を入口にして読み進めてみましょう。
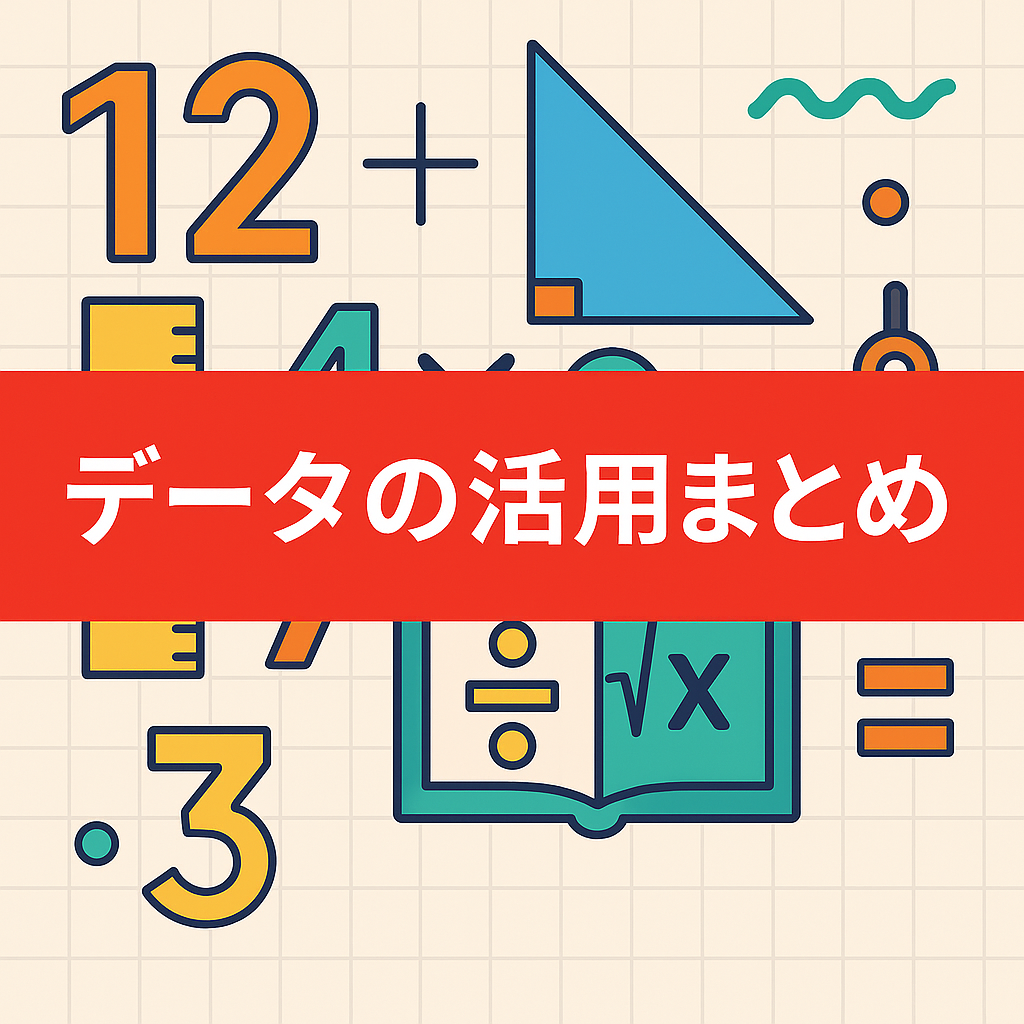

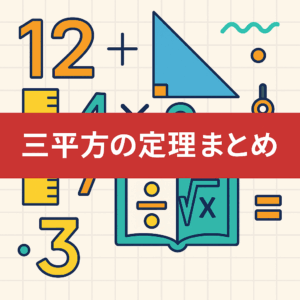
コメント