導入
中2までの確率では、サイコロやコインのように「順序を区別する事象」が中心でした。
しかし中3では一歩進んで、**順序を考えない選び方(組合せ)**を使った確率を学びます。
カードやくじ引きなど、「どの順番で選んでも同じ結果」になる場面が多く、
この考え方は入試でも頻出です。
この記事では、**樹形図を使って“順序をなくす”**考え方を通じて、
組合せを自然に理解できるように説明します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
組合せとは?
| 種類 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 順列 | 順序を区別して並べる | (A,B) と (B,A) は別の結果 |
| 組合せ | 順序を考えずに選ぶ | (A,B) と (B,A) は同じ選び方 |
樹形図で考える
例題①:A・B・Cの3人から2人を選ぶとき、何通りあるか?
まず、順序を考える場合の樹形図をかきます。
A → B、C
B → A、C
C → A、B
全部で6通り(A,B/A,C/B,A/B,C/C,A/C,B)。
でも、(A,B) と (B,A) は同じペアなので、順序を考えないなら重複をなくす必要があります。
「順序を消していく」考え方
樹形図を書くときに、
✅ すでに出た組み合わせは、次から書かない(消していく)
ようにすればOKです。
A → B、C
B → (Aは消す)→ C
C → (AとBは消す)
残るのは
A-B、A-C、B-C の3通り。
これが「3人から2人を選ぶ組合せの数」です。
組合せを使った確率の考え方
確率の基本はいつも同じです。確率=有利な選び方全体の選び方確率=全体の選び方有利な選び方
例題②:赤玉5個・白玉3個の袋から2個取り出す
- 全体の選び方
まず8個から2個を選ぶ。
順序を考えると 8×7=56 通り。
でも (A,B) と (B,A) は同じだから、半分にして 28通り。 - 有利な選び方(赤2個)
赤玉5個から2個を選ぶ。
順序を考えると 5×4=20 通り。
同様に半分にして 10通り。 - 確率
10 ÷ 28 = 5/14
💡「2つの順序を考えない=半分にする」というイメージを持たせると、中学生にも直感的に伝わります。
例題③:A・B・C・Dの4枚のカードから2枚を同時に選ぶとき
全体の選び方は次のように考えます👇
A → B,C,D
B → (Aは消す)→ C,D
C → (A,Bは消す)→ D
D → (A,B,Cは消す)
→ 組合せは 6通り。
(A,B)(A,C)(A,D)(B,C)(B,D)(C,D)
注意点
| ケース | 順序 | 使う考え方 |
|---|---|---|
| サイコロ2回ふる | 順序あり | 樹形図 or 表で全部書く |
| くじを同時に2枚引く | 順序なし | 樹形図で重複を消す(組合せ) |
🔹「順序がある? ない?」を毎回確認するクセをつけるのがコツ。
まとめ
- 組合せ=順序を考えずに選ぶ方法
- 樹形図を書くときは、出たものを1つずつ消していくと重複しない
- 確率=有利な選び方 ÷ 全体の選び方
- サイコロは順序あり、くじ・カードは順序なし
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理


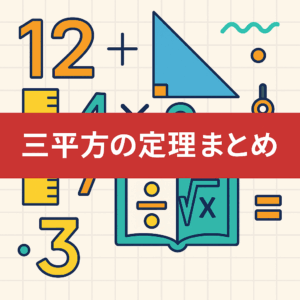
コメント