導入
「平均は同じなのに、データの感じが全然ちがう」──こんなときに役立つのが「散らばり(ばらつき)」を表す方法です。
中1数学ではまず「範囲(レンジ)」を学びます。これはとてもシンプルですが、データの広がりをつかむ第一歩になります。さらに発展的な内容として「四分位範囲」という考え方もあります。
この記事では、データの散らばりを表す基本的な方法を整理します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
範囲(レンジ)とは?
- 定義:最大値 − 最小値
- 意味:データがどれくらい広がっているかを表す。
- 特徴:計算が簡単でわかりやすい。
例
テストの点数が「50, 60, 70, 80, 100」のとき、
範囲=100 − 50 = 50点。
👉 平均が同じでも、範囲が大きければデータはばらつきが大きい。
散らばりを見る理由
- 平均だけだと「実際の状況」がわからないことがある。
- 範囲を調べることで「安定しているのか」「バラバラなのか」が見えてくる。
例
- Aクラス:平均70点、範囲10点(→ みんな同じくらい)
- Bクラス:平均70点、範囲50点(→ 点数が大きく分かれている)
同じ平均でも、クラスの雰囲気はまったくちがう!
発展:四分位範囲(しぶんいはんい)
※中1では必須ではないが、知っておくと高校以降につながる内容。
- 考え方:データを小さい順に並べ、4つに分ける。
- 四分位範囲:上位25%の境界(Q3)− 下位25%の境界(Q1)
- 特徴:外れ値に強く、データの「真ん中あたりの散らばり」を表せる。
👉 高校で本格的に学ぶが、中学のうちに「平均・中央値・範囲の次に出てくる指標」として軽く触れておくと理解がスムーズ。
まとめ
- 範囲=最大値 − 最小値で散らばりを表す
- 同じ平均でも範囲がちがえばデータの性質は大きく変わる
- 発展的には「四分位範囲」で、外れ値に強い散らばりの指標もある
中1では「範囲」をしっかりマスターすることが大切です。これが次に学ぶ「データの分析力」につながります。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ
次に読むならこちらもおすすめです。
🔗 中1方程式の教え方まとめ|教材シリーズはこちら

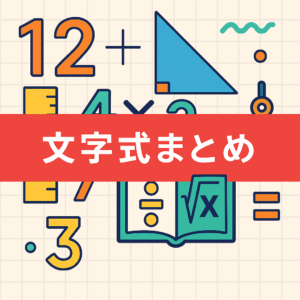
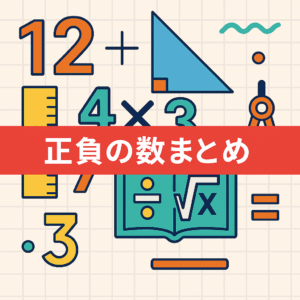
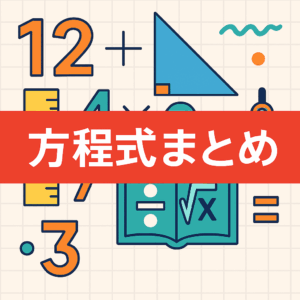
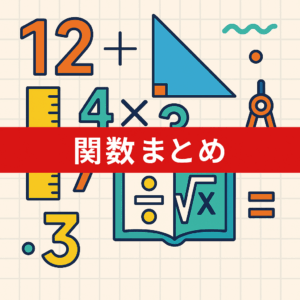
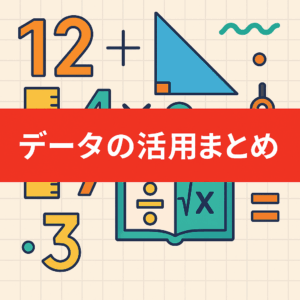

コメント