導入
中学1年生の数学で学ぶ「データの活用」。その中でも最初に登場するのが「代表値(だいひょうち)」です。
代表値とは、たくさんのデータを1つの数でまとめるときに使う指標のこと。代表値には「平均」「中央値」「最頻値」の3つがあります。
一見すると似ているように見えますが、それぞれ役割や特徴がちがいます。この記事では、中1で必ず押さえておきたい代表値の意味と使い分けを、具体例とあわせて解説します。
この記事は中学数学「データの活用」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「データの活用」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
ポイント
平均値(へいきんち)
- 計算方法:すべてのデータの合計 ÷ データの個数。
- 特徴:全体を「ならした値」としてイメージしやすい。
- 弱点:極端に大きな値や小さな値(外れ値)があると大きくずれる。
例
テストの点数が「50, 60, 70, 80, 100」のとき、
平均=(50+60+70+80+100)÷5=72点。
中央値(ちゅうおうち/メジアン)
- 計算方法:小さい順に並べて、真ん中にある値。
- 特徴:外れ値の影響を受けにくい。
- 使いどころ:「典型的な1人」を表したいときに便利。
例
点数が「50, 60, 70, 80, 100」のとき、
並べたときの真ん中=70点。
※もしデータが偶数個なら、真ん中2つの平均をとる。
最頻値(さいひんち/モード)
- 計算方法:一番多く出てきた値。
- 特徴:人気や傾向をつかみやすい。
- 使いどころ:ファッションのサイズ、売れ筋の商品など。
例
サイズが「M, M, M, L, L, S」なら、
最頻値=M。
3つの代表値をどう使い分ける?
- 平均値:全体像をつかむときに有効。
- 中央値:外れ値に左右されない実感値を知りたいとき。
- 最頻値:一番多いもの・流行をつかみたいとき。
同じデータでも「どの代表値を選ぶか」で見え方が変わります。ここが“算数”とちがい、“数学らしさ”を感じられるポイントです。
まとめ
中1で学ぶ代表値は、
- 平均値=全体をならす数
- 中央値=真ん中の数
- 最頻値=一番多い数
この3つをしっかり区別することが大切です。
代表値はテストや調査だけでなく、ニュースや日常生活でも頻繁に登場します。これを理解しておけば、情報を正しく読み取る力がぐんと伸びます。
他の関連記事もまとめてあるので、ぜひこちらからチェック!
👉 データの活用まとめページ
次に読むならこちらもおすすめです。
🔗 中1方程式の教え方まとめ|教材シリーズはこちら

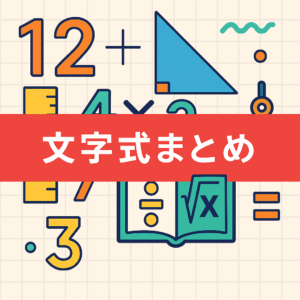
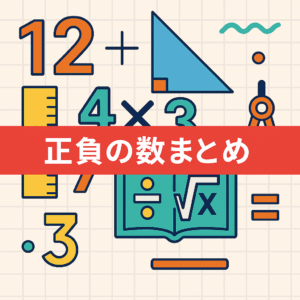
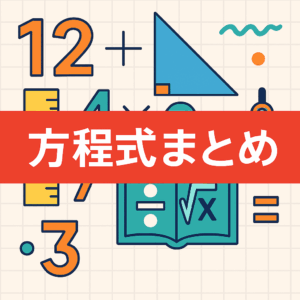
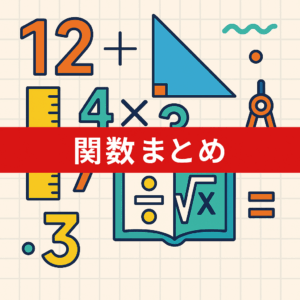
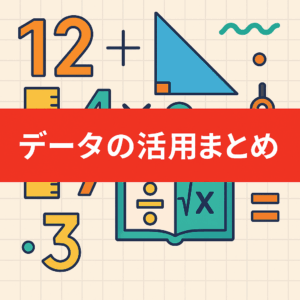

コメント