はじめに:「この2本、平行です」ってどういうこと?
一次関数のグラフを2本並べて見せたとき、
「これ、平行です」
「じゃあ式にはどんな特徴がある?」
と聞いても、aやbとの関係まで答えられる生徒は意外と少ないものです。
式とグラフの形をつなげて理解するには、「傾き=a」に注目する必要があります。
👉 本記事は 中学数学「関数」まとめ の一部です。比例・反比例・一次関数を体系的に整理した一覧はこちらから。
ポイント①:傾き(a)が同じなら、どこまでも平行
まず押さえておくべき基本は、
一次関数のグラフは、a(傾き)が同じなら必ず平行になる
なぜなら傾きとは、
- xが1増えたときに、yがいくつ増えるか(=変化の割合)
を表しているから。
- y = 2x + 1
- y = 2x − 4
→ どちらも「右に1行ったら、上に2上がる」同じペースの直線。
→ だから平行になる!
ポイント②:b(切片)が違うと「高さ」だけがずれる
傾きが同じでも、bの値(y切片)が違えば、y軸のどこを通るかが変わります。
つまり:
- aが同じ → 角度は同じ → 平行
- bが違う → y軸との交点が違う → 上下にズレる
この感覚を実際にグラフを見せて比較させると、「bは高さ」として定着しやすくなります。
ポイント③:平行なグラフを見て、式の“a”を見抜かせる
逆に、グラフが平行になっているのを見たら、
「この2本、aは同じだね!」
と式の中身に目を向けさせると良い練習になります。
また、問題として:
- 「この式と平行な直線の式を作れ」
→ aはそのまま、bだけ変えればOK
というように、平行=a固定・bだけ調整という型を覚えさせると、柔軟な操作も可能になります。
まとめ:平行な関数=「aが同じ」だけでOK!
一次関数のグラフで「平行」かどうかを見分ける最大のポイントは、aが同じかどうか。
bは上下のズレにすぎないので、式が違っていても「傾きが同じ」ならグラフは必ず平行です。
この構造をしっかり押さえることで、式とグラフの対応関係が明確になります。
👉 本記事は 中学数学「関数」まとめ の一部です。比例・反比例・一次関数を体系的に整理した一覧はこちらから。

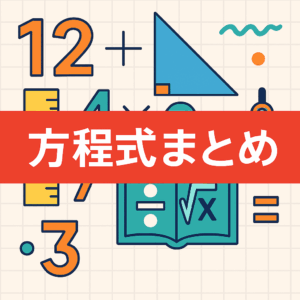
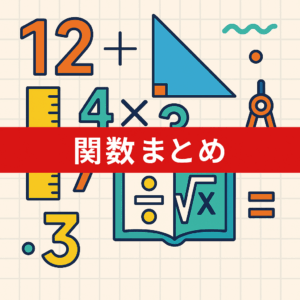
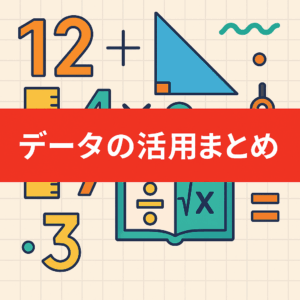

コメント