目次
導入
「二次方程式って、どの方法で解けばいいの?」
「毎回、解の公式を使っていいの?」
そんなふうに迷う人は多いです。
実は、二次方程式には**“解く順番”**があります。
まずは右辺を0にして整理し、因数分解できるかを確認。
できない場合だけ、最後の手段として解の公式を使えばOKです。
この記事では、「どうやって判断するか」「どの順で解くか」を
中学生にもわかりやすく解説します。
この記事は中学数学「方程式」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「方程式」まとめ|中1〜中3を体系的に整理
基本の流れ
① 右辺が0になるように移項
② 左辺が因数分解できるか確認
③ できなければ平方完成や解の公式で解く
例題1:x² + 5 = 2x
まずは移項して右辺を0に:
x² - 2x + 5 = 0因数分解できないので、解の公式で:
x = {2 ± √(4 - 20)} / 2 = 1 ± √(-4)→ 実数解なし
例題2:x² = -4x + 5
移項して整理:
x² + 4x - 5 = 0因数分解できる!
(x + 5)(x - 1) = 0 → x = -5, 1→ このように、まずは整理してから判断するのがポイント
判断のコツ
- 「x² の係数が1」で「整数解っぽい」なら因数分解を試す
- 因数分解できない or 難しそう → 平方完成 or 解の公式
- 平方完成は途中式が複雑 → テストでは解の公式の方が早いことも
練習問題
問題1:次の方程式を移項してから因数分解で解け
x² = 3x + 10
x² + 1 = -4x問題2:因数分解ができなければ解の公式で解け
2x² + 5x + 3 = 0
x² + x + 1 = 0まとめ
- 右辺を0にするのが最優先
- まず因数分解できるか見てみる
- できなければ解の公式は頼れる武器!
この記事は中学数学「方程式」シリーズの一部です。
👉 中1〜中3の流れを体系的に整理したまとめ記事はこちら
中学数学「方程式」まとめ|中1〜中3を体系的に整理


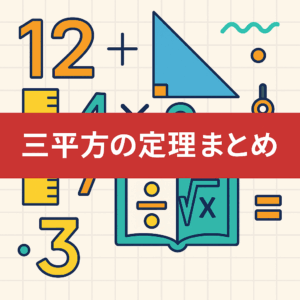
コメント